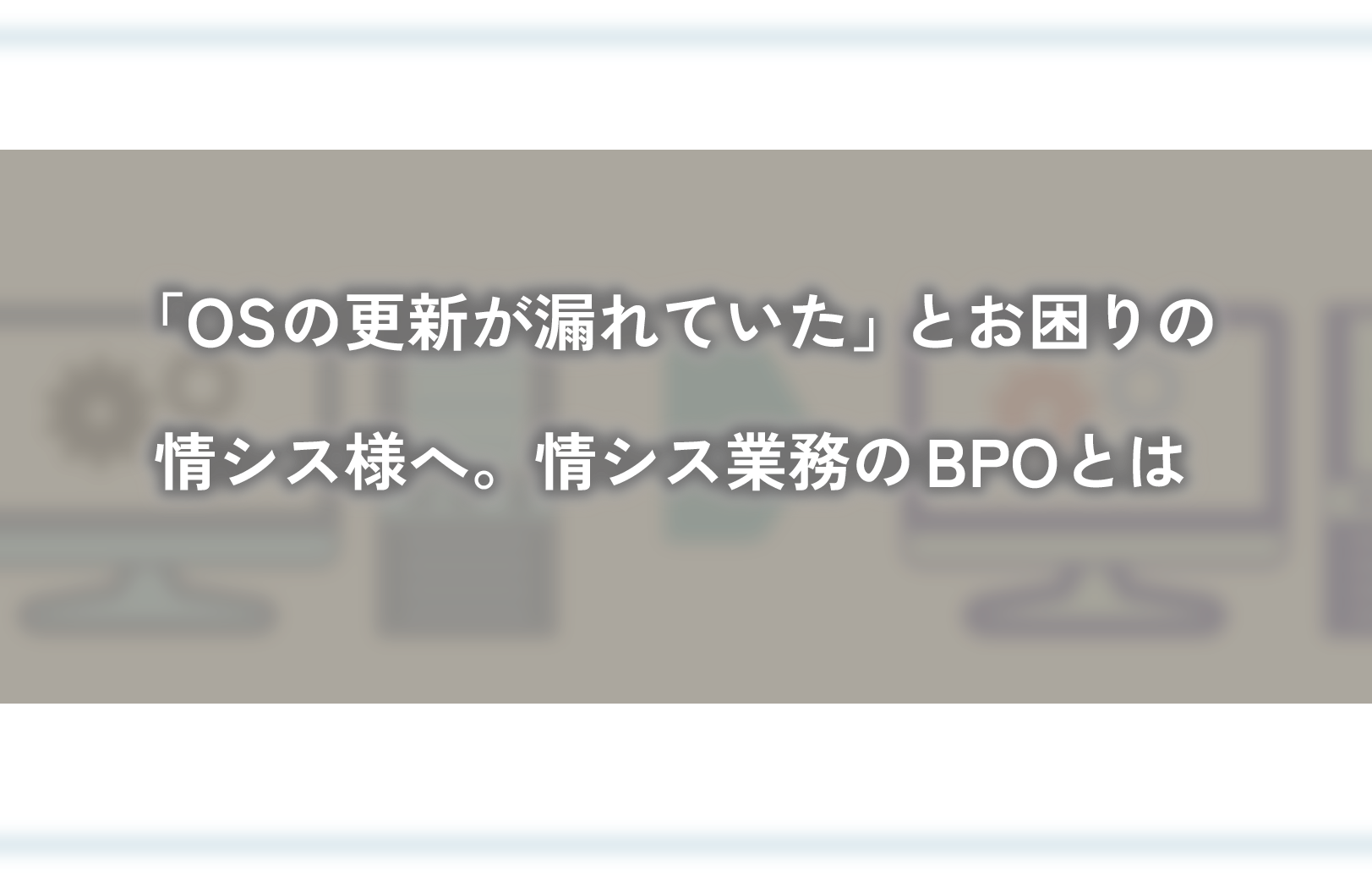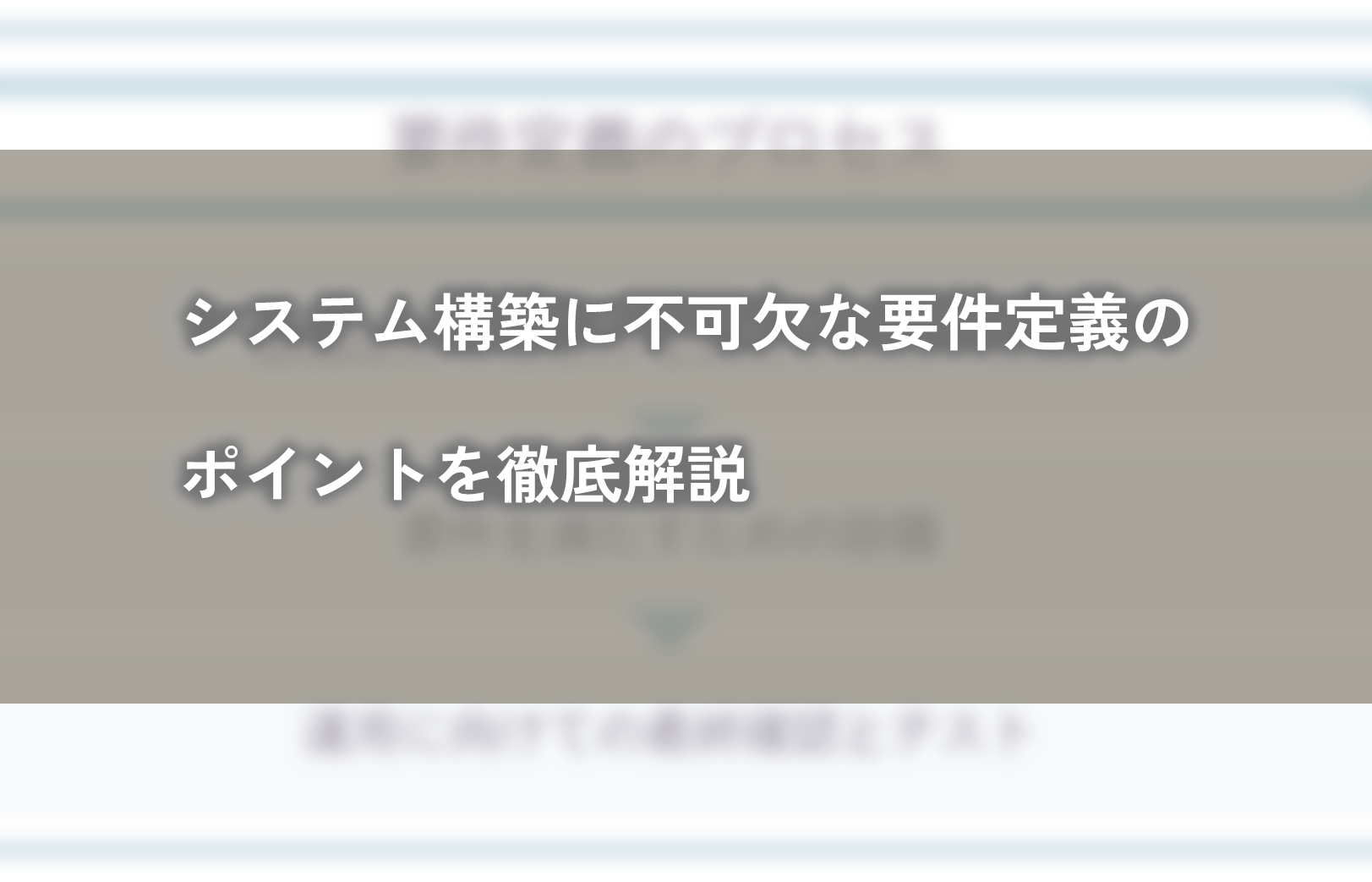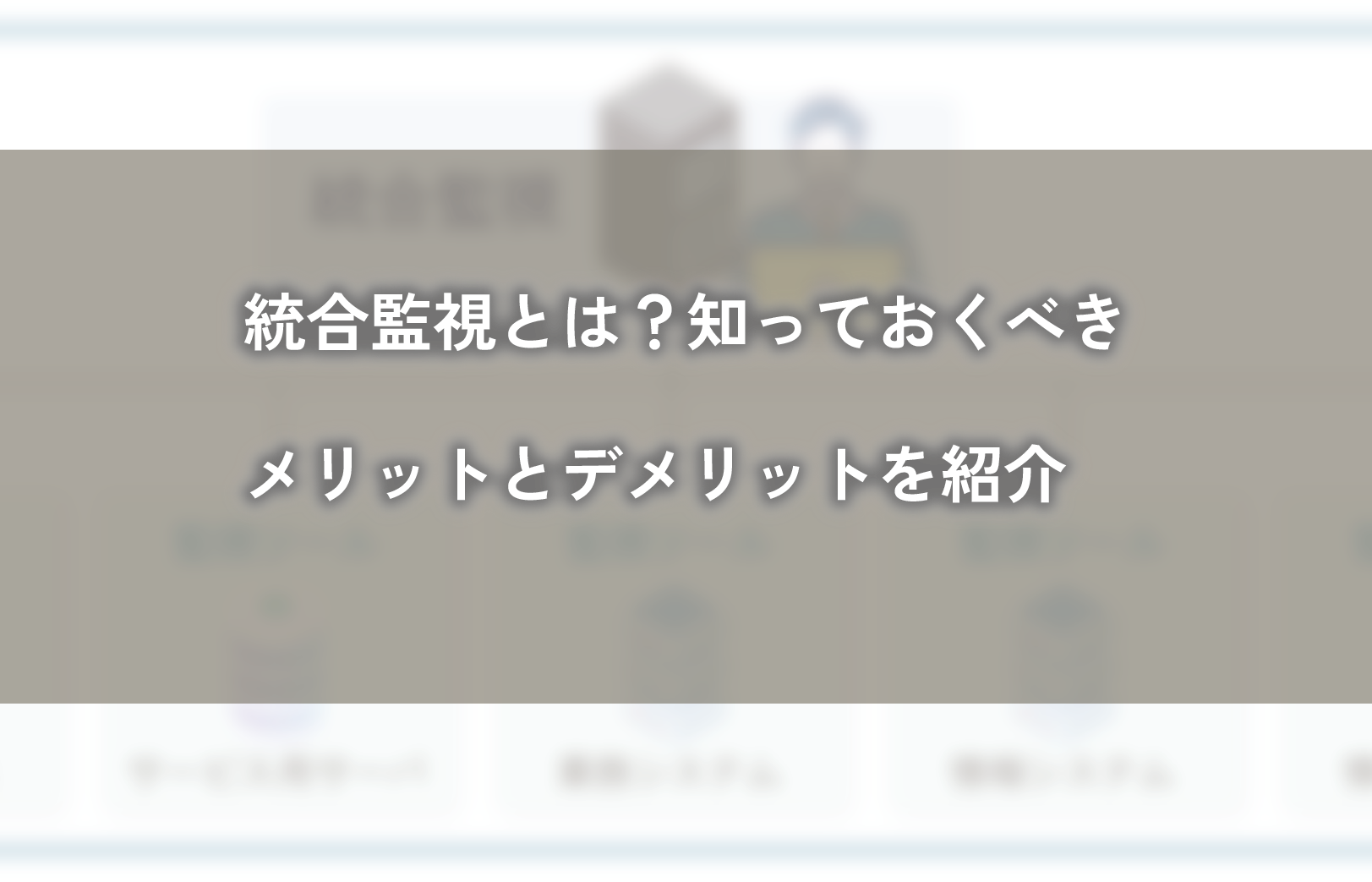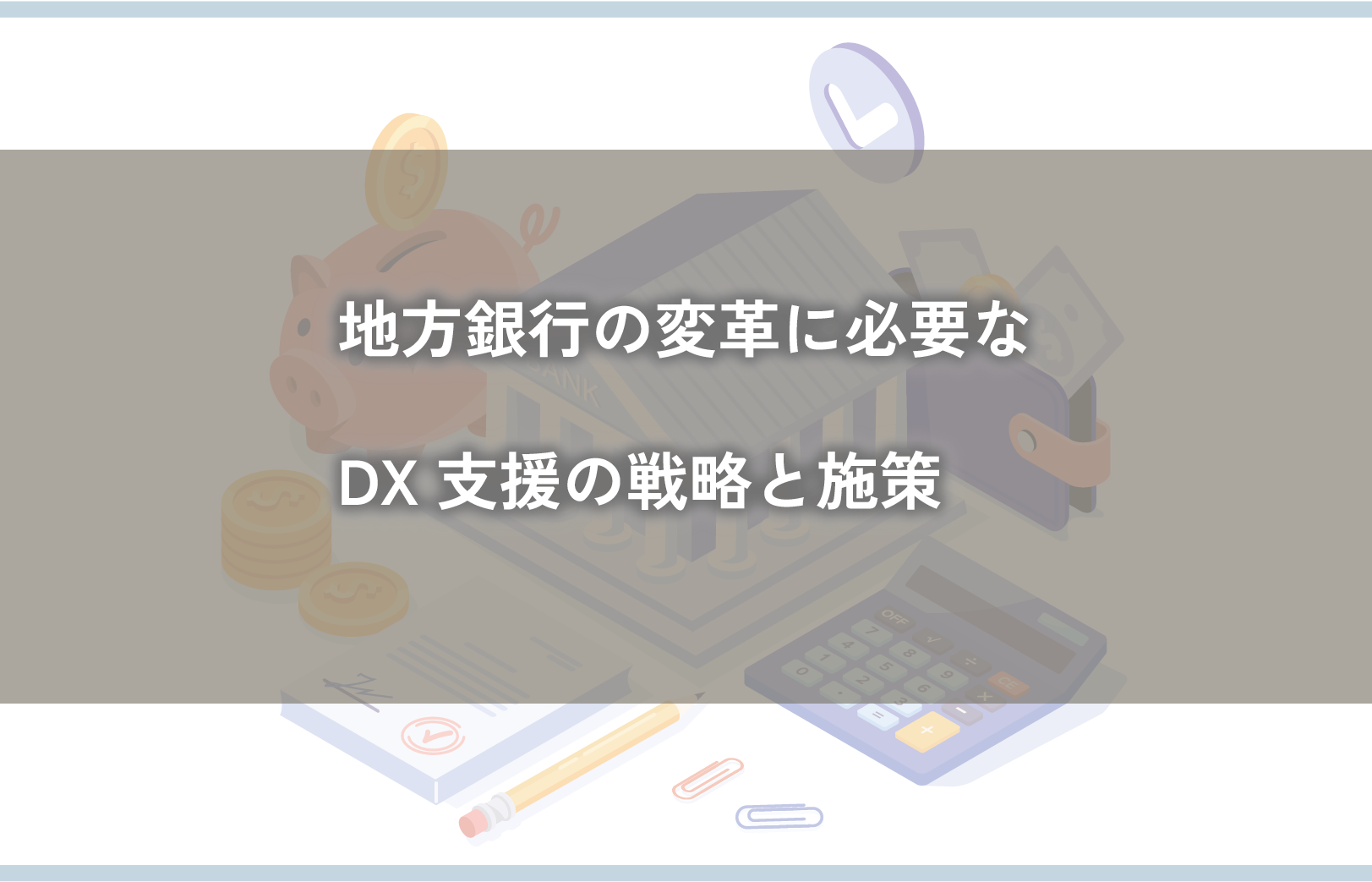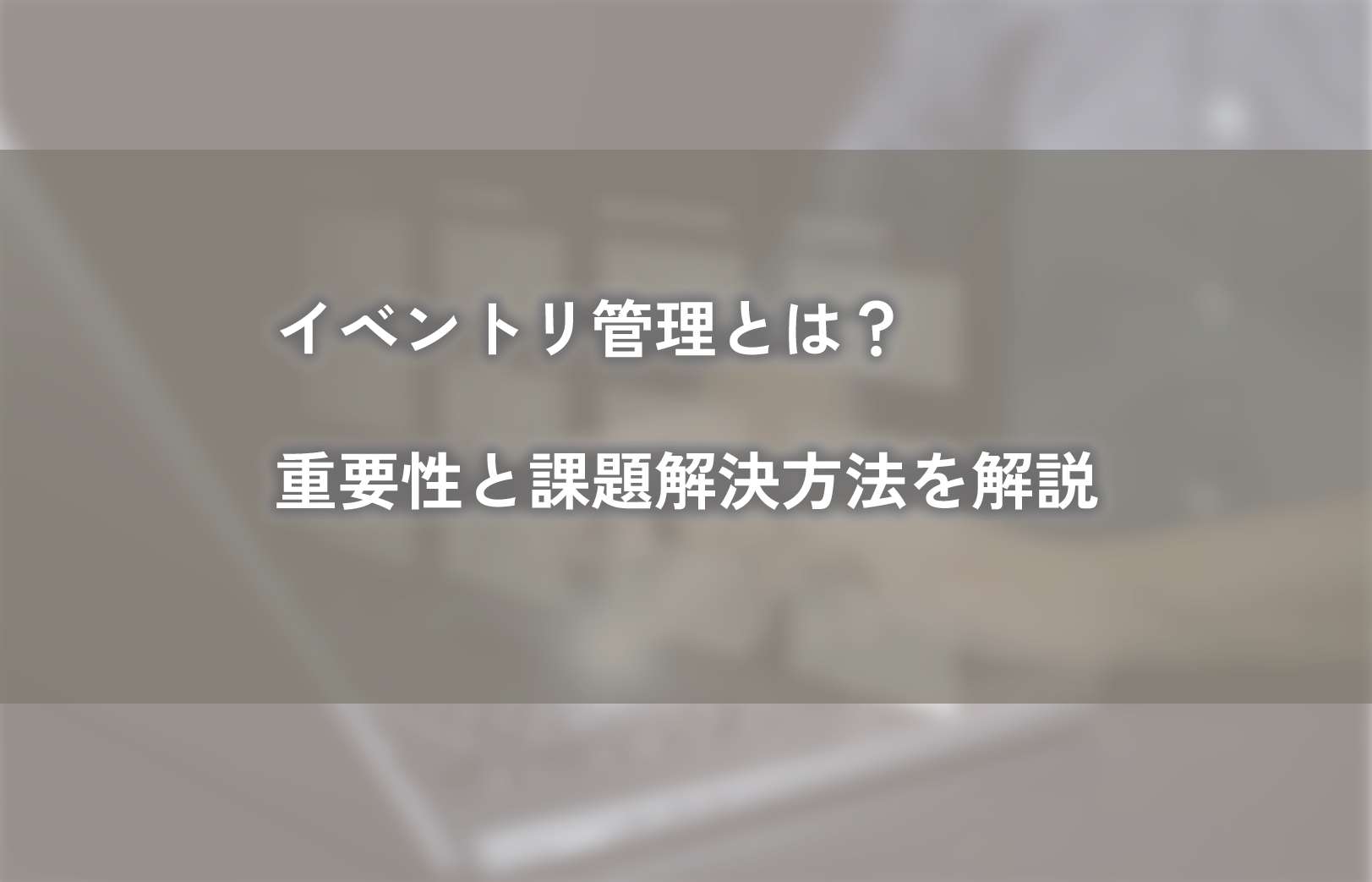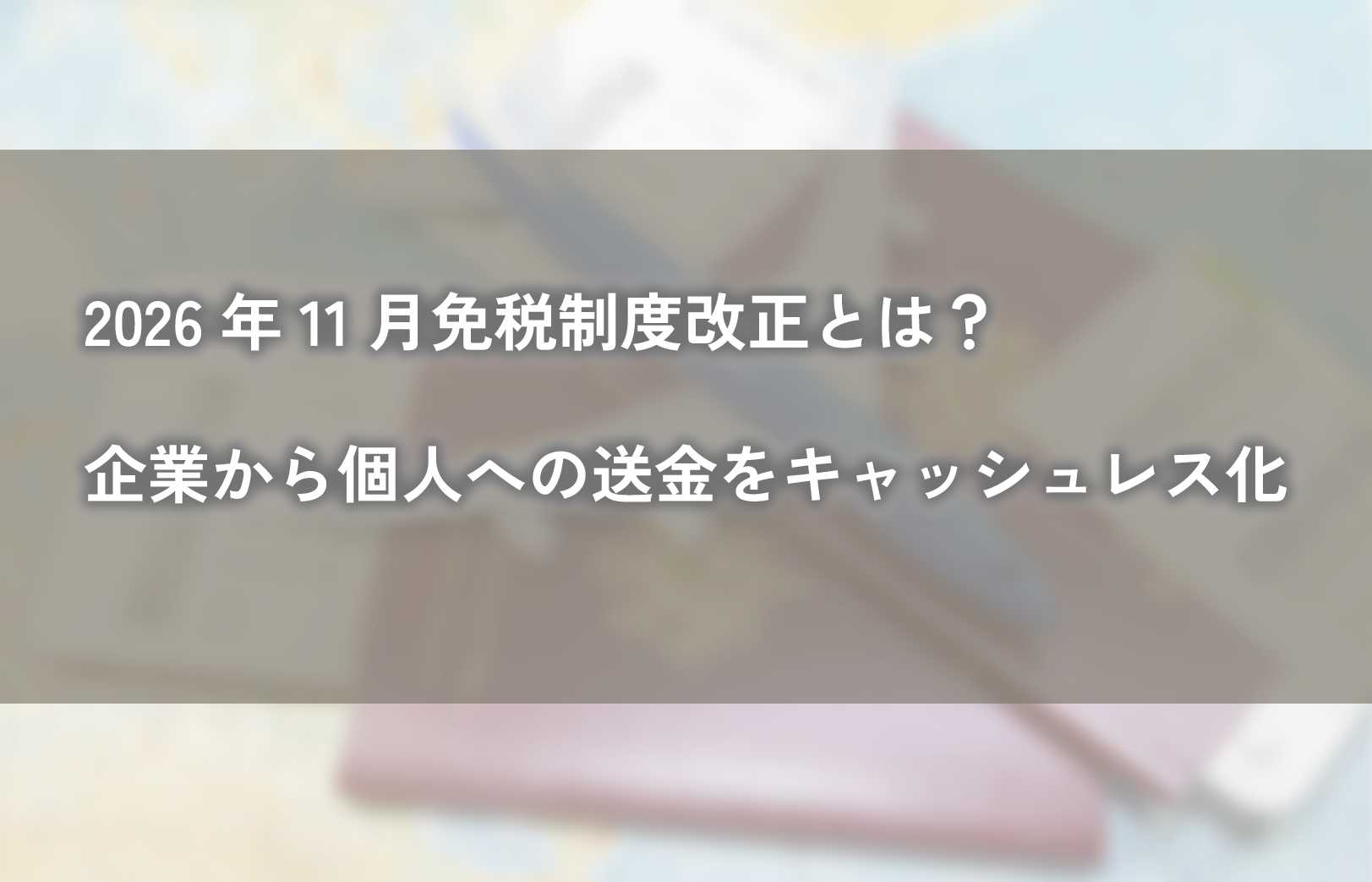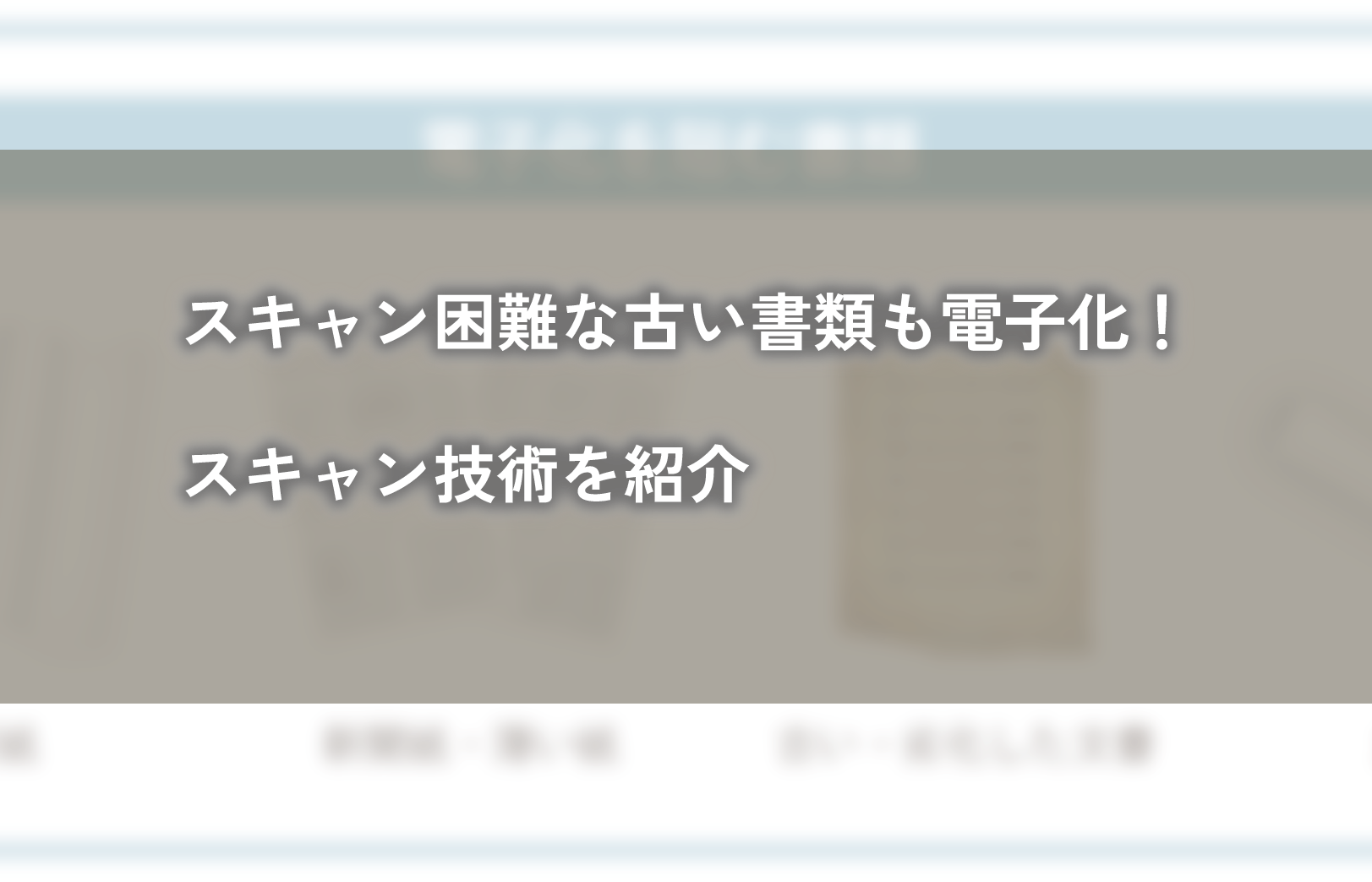これだけは知っておきたい!システム構築の基礎知識
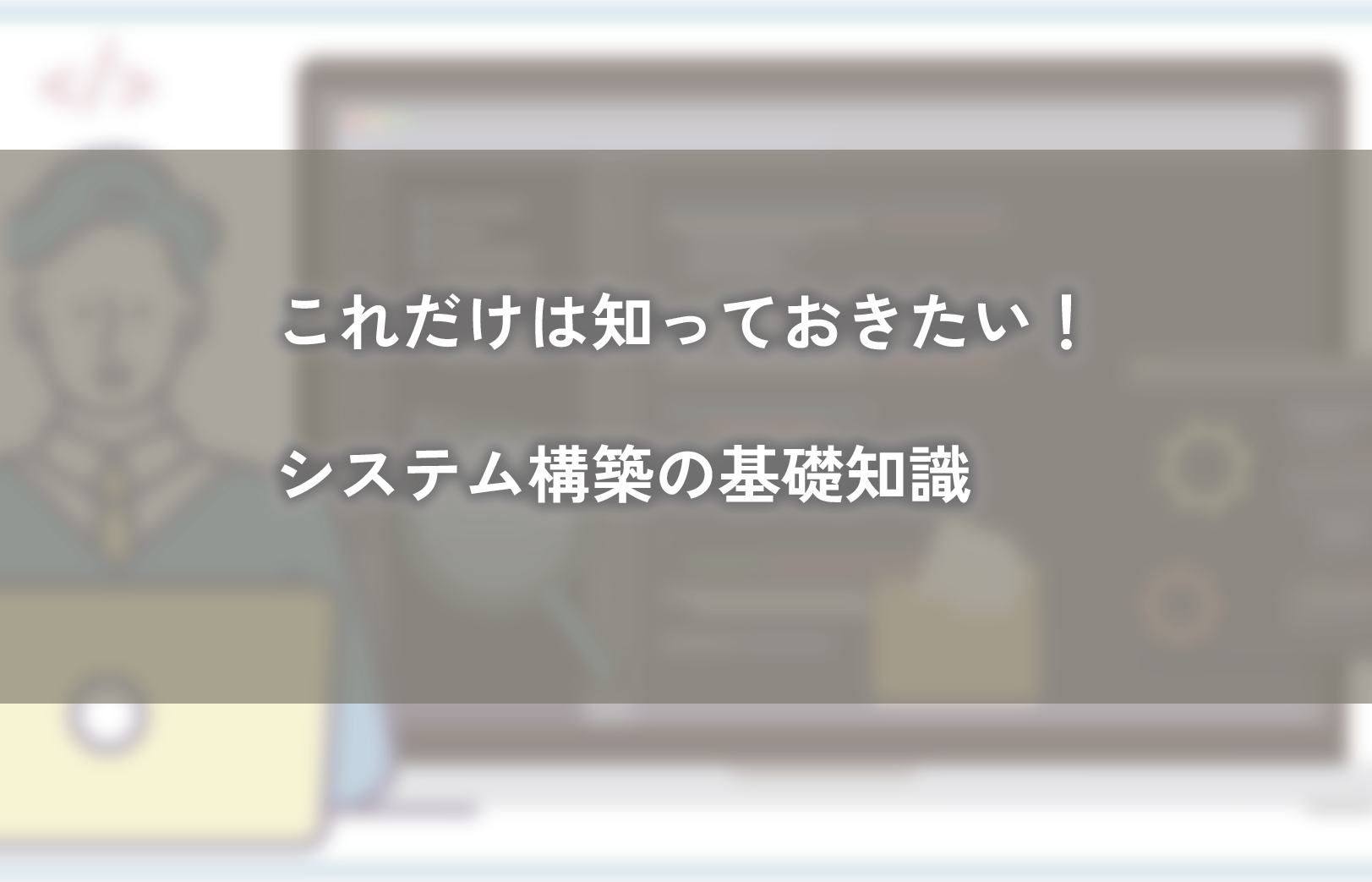
現代のビジネス環境においては、効率的な業務運営が求められておりますが、適切なシステム構築の基礎知識が不足したまま取り組むと、導入後のトラブルや非効率な運用が問題となることも少なくありません。そのような悩みを抱える方々に向けて、本記事では「システム構築」と「システム開発」の違いから、フルスクラッチ開発とパッケージ開発のメリットやデメリット、システム部品組み合わせ型についてなど、システム構築において不可欠な基礎知識を解説します。
システム構築とは?
システム構築とは単にプログラムを作るだけではなく、企業の業務ニーズや課題解決に応じ、情報技術を駆使して機能的なシステムを設計、開発、導入する一連の活動を指します。業務効率化やデータ管理の精度向上、顧客サービスの改善など、多岐にわたる目的を達成するために行われます。
近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)が進む中、システム構築は単なる技術導入に留まらず、企業の成長戦略において重要な役割を果たします。迅速な市場対応や経営判断を支えるリアルタイムデータ分析を可能にし、企業の競争力と独自の優位性を高める基盤となります。
システム開発だけではなく、そのシステムやソフトウェアを動かすためのサーバやネットワークといったハードウェアの選定や導入、各種設定、そして完成したシステムの運用・保守まで、幅広い工程を含んでいます。
システム構築は、初期段階から綿密な計画と段階的な実装が求められ、多くの専門知識が必要です。業界特有のニーズや法規制への対応も考慮に入れ、構築したシステムの維持管理やアップデートも含めて、長期的な運用を見据えた信頼性と可用性が重視されます。
「システム構築」と「システム開発」の違いとは
システム構築とシステム開発は混同されがちですが、それぞれ異なる意味を持っています。両者の違いを理解するには、システム構築は「できたものを組み立てる」、システム開発は「新しいものを作る」、という視点が役立ちます。そのため「システム構築」という大きな箱の中に、「システム開発」という作業が入っているイメージです。
まずシステム開発は、要件定義をもとに設計を行い、プログラミングで機能を実装し、それが正しく動くかテストするまでを指します。
企業の独自の要件に応じて一から機能を設計し、カスタマイズされたソリューションを提供することが中心となり、他にない独自の機能を求めるプロジェクトや、長期的なビジョンに基づくシステム設計が必要な場合に適しています。
システム構築はシステム開発だけでなく、そのシステムを動かすために必要なサーバやパソコンなどハードウェアの選定や設置、ネットワークの設定を行い、完成したシステムの導入、運用や保守まで含みます。
適切な技術戦略を立案するためには、システム構築とシステム開発の違いを理解することが重要となります。
なぜシステム構築が重要なのか
現代のビジネスはITシステムなしでは成り立たなくなりつつあります。人の手で行っていた作業をシステムに置き換えることで、時間、コスト、労力を大幅に削減することができます。ビジネスを効率的に動かすためには、しっかりとしたシステムが欠かせません。システム構築は業務を自動化や効率化を促進し、人的ミスを減少させることでコスト削減を実現します。
例えば、卸売・小売業や製造業などの業界においては、システム構築によって、受注から出荷までの一連の運用を効率化し、リアルタイムでの情報共有が可能になります。これにより、単に受注から出荷までを迅速にするだけではなく競争力を高めることができます。
商品を受け取る顧客にとっても「注文した商品が、速く、正確に届く」ことにより、顧客満足度の向上にも寄与します。
顧客データを一元管理し、サービスを提供することで、顧客との関係を強化できます。特にECサイトでは、購入履歴や嗜好に基づくレコメンデーション機能を通じて、顧客体験を向上させることが重要です。
システム構築はビジネスの柔軟性を高めます。企業が成長するにつれて、システムの拡張性や柔軟性が求められます。オーダーメイドのシステムは、企業の特定のニーズに合わせて設計されているため、業務の量の増減に応じて、柔軟に性能や規模を変更できます。
適切に構築されたシステムは、最新のセキュリティ基準に準拠し、データ漏えいや不正アクセスから企業を守ります。
システム構築は業務効率化、顧客満足度向上、ビジネスの柔軟性、セキュリティ強化といった多方面で企業の成功を支える重要な要素といえるのです。
システム構築のプロセス
システム構築は、単にプログラムを作るだけでなく、完成したシステムが安定して稼働し、ビジネスの目的達成までの一連の活動を指します。このプロセスは、主に以下の4つの段階で構成されています。
要件定義
要件定義は、システム構築の初期段階で、構築するシステムの目的や機能、性能を明確にする過程です。クライアントなどの要望を正確に把握しプロジェクト関係者全員の認識のズレをなくします。
要件定義書は、プロジェクト関係者全員が同じ目的を一致させるための基礎の部分となり最も重要な部分です。これにより、スムーズなプロジェクト進行を実現します。
設計と計画
要件定義を基に、システム構成や実装する機能、予算やスケジュールや体制などを決める工程です。
基本設計書に、どのようなシステムを構築するのか、構築するためには誰が必要なのか、いつまでに何を完成させるかなどを詳細に記載します。
必要な人員やスケジュールを計画し、効率的な進行を目指します。設計と計画の段階が、プロジェクトの成功を左右します。
実装とテスト
実装とテストはシステム開発の重要なプロセスです。実装では設計に基づいてプログラムを作成し、テストではそのプログラムが正しく機能するかを検証します。エラーが発生した場合は、改修を行います。
運用と保守
システム構築が完了したら終わりではなく、安定して稼働するためには運用と保守が必要になります。
不具合が発生したら改修を行ったり、必要に応じてシステムの更新や改善を行います。不具合を起こさないためにも、定期的なメンテナンスやアップデートが必要になります。
フルスクラッチ開発とパッケージ開発の違い
フルスクラッチ開発とパッケージ開発の違いについて、メリットだけでなく、デメリットについても紹介します。
フルスクラッチ開発のメリット
フルスクラッチ開発の最大のメリットは、圧倒的な自由度です。既存のパッケージやテンプレートに縛られることなく、企業の独自の業務プロセスや特定の要件に完全に合致したシステムをフルオーダーメイドで構築できます。必要な機能だけを実装するため、無駄な機能がなく、シンプルで高速なシステムが実現します。また、将来の事業拡大や技術の変化にも柔軟に対応できるよう、高い拡張性を持たせた設計が可能です。
フルスクラッチ開発のデメリット
一方で、デメリットも無視できません。ゼロから全てを開発するため、開発コストは高くなりがちです。また、要件定義から実装、テストまで全ての工程をフルオーダーメイドで行うため、開発期間が長期化する傾向にあります。これにより、例えば新規市場開拓の際に市場投入のタイミングが遅れるリスクも伴います。加えて、高度な技術力と豊富な経験を持つ人材が不可欠であり、適切なスキルを持つ開発者を確保できなければ、プロジェクトの成功が難しくなるという課題もあります。
パッケージ開発のメリット
パッケージ開発の最大のメリットは、開発コストと期間の削減です。ゼロからシステムを構築する必要がないため、初期費用を抑えることができ、短期間でシステムを導入して運用を開始できます。また、多くのユーザに利用されているパッケージ製品は、信頼性が高く、不具合が少ない傾向にあります。提供元企業によっては、サポートやメンテナンスも充実しているため、自社で保守・運用を行う負担が軽減されます。
パッケージ開発のデメリット
一方、パッケージ開発のデメリットは、カスタマイズの制限です。パッケージは汎用的に作られているため、自社の独自の細かな要件に合わないことがあります。その場合、システムに合わせて業務フローを変更しなければならないケースも出てきます。また、カスタマイズを過度に行うと、結果的にフルスクラッチ開発よりもコストが高くなる可能性もあります。
システム部品組み合わせ型とは

システム部品組み合わせ型開発の良さは、柔軟なシステム構築とコスト・期間の削減を両立できることです。
フルスクラッチ開発のようにゼロから全てを開発するのではなく、決済システムや認証機能、地図表示といった、すでに提供されている高品質なサービスやソフトウェア部品を組み合わせてシステムを構築します。必要な機能だけを効率的に組み合わせることができ、開発期間とコストを大幅に抑えながら、独自の要件に合わせた柔軟なシステムを短期間で実現できます。
また、各部品は専門企業が開発・保守を行っているため、常に最新の技術やセキュリティ対策が施されているという安心感があります。新しい技術を取り入れたい場合も、新しい部品を組み合わせることで、将来的な拡張性にも優れているのが大きな利点です。
まとめ:システム構築のことならヤマトシステム開発にご相談を
ヤマトシステム開発は、多様な業界での実績を有し、効率的なシステム構築を支援します。パッケージ製品では対応できない、お客さまの固有の課題解決に対応したシステムを構築します。
企画・要件定義から、設計、開発、導入、そしてリリース後の運用保守まで、すべてをワンストップでサポートし、お客さまのビジネスを支えます。 詳細な説明や、具体的な課題やご要望がございましたら、ぜひご相談ください。
関連サービス

- システム構築サービス
- ご要望に合わせた柔軟なシステムを構築!既存システムとのデータ連携も可能で、業務受託や運用監視まで安定運用を提供いたします。